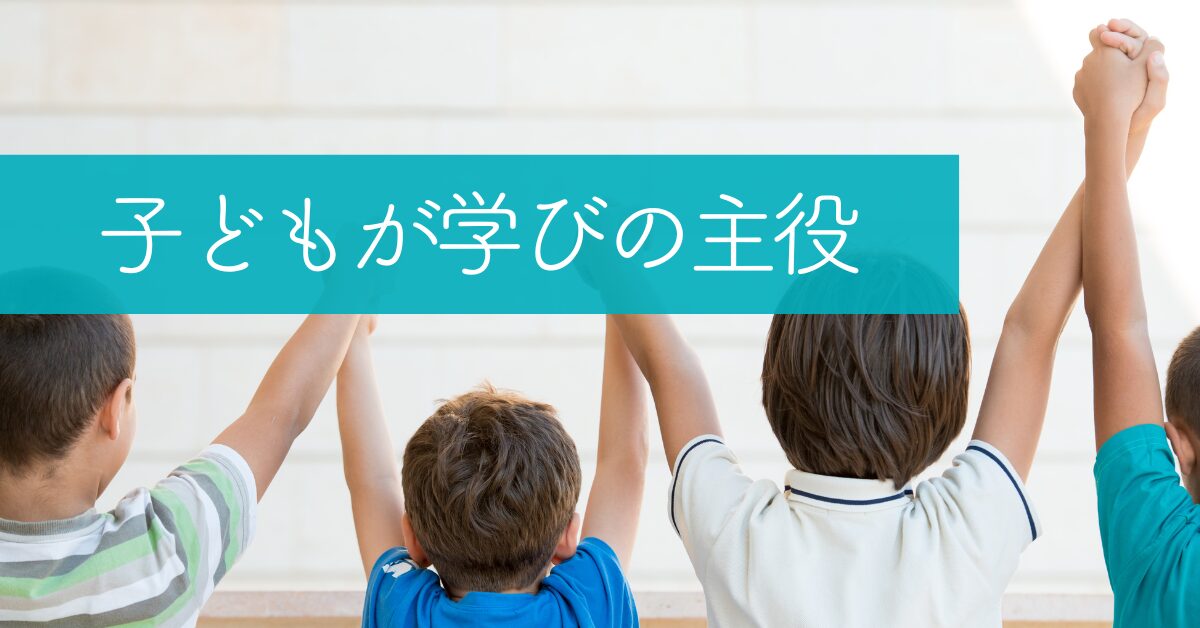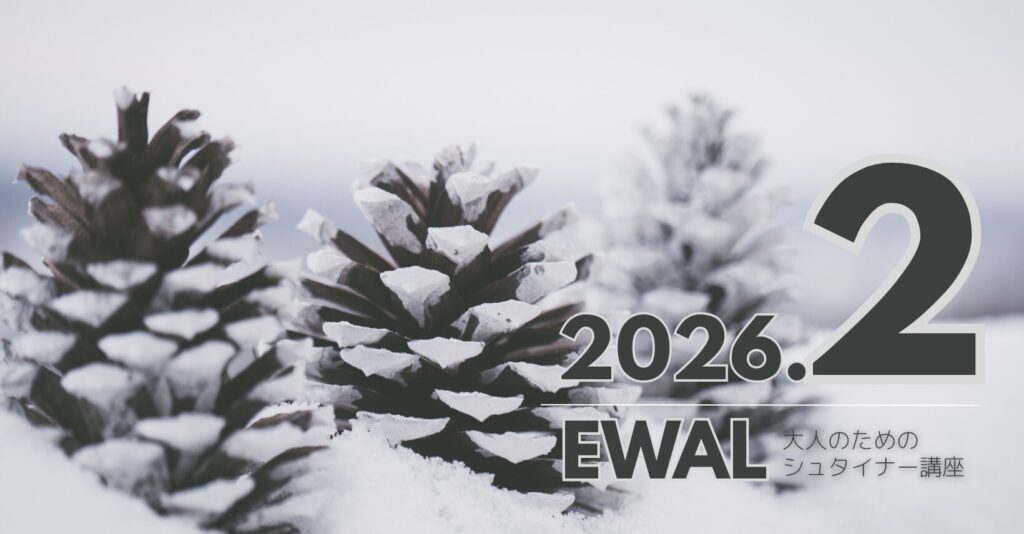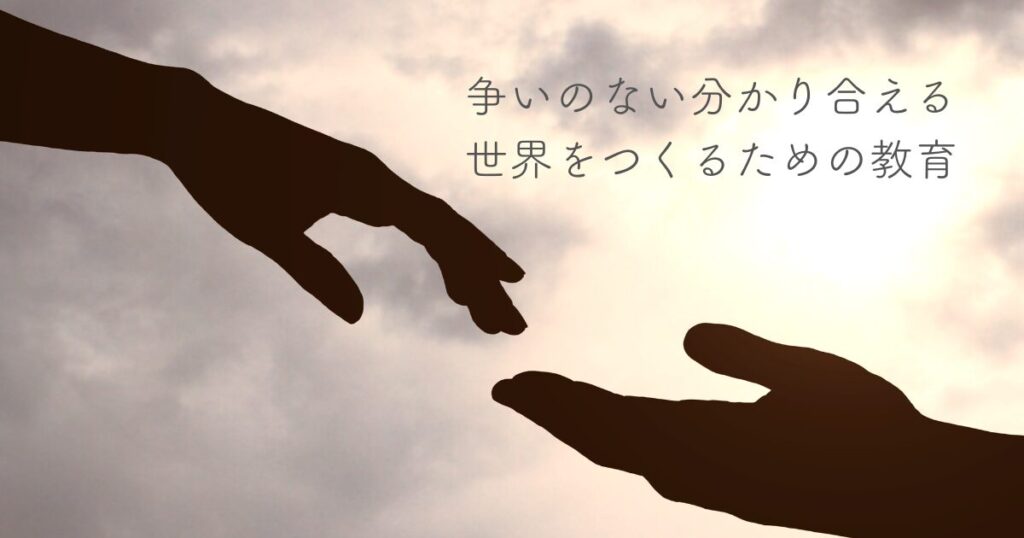本記事は、シュタイナー専門家石川華代のメルマガを元に記事にしています。
教えずに導くという選択——学びを遠ざけないために
シュタイナー教育に学ぶ子どもの力を引き出し方
東京大学の光吉俊二教授が提唱する「四則和算」。
このユニークな研究グループには、大学教授や学校教員、教育関係者など、シュタイナー教育とは縁のない専門家たちが多く参加しています。
そのプロジェクトに関わっているシュタイナー教育専門家 石川華代は、先日日本に一時帰国した際、このグループの仲間たちに向けてシュタイナー数学のワークショップを行いました。
驚かれたのは「言葉の少なさ」
ワークショップではみなさん、驚かれます。
その言葉の少なさに。
石川華代のシュタイナーアプローチは、
「的確な言葉を、必要最小限だけ伝える」というもの。
子どもや受講生が夢中になっているとき、
ほとんど言葉を発しません。
ただ、静かに見守ります。
そんなレッスンの様子に驚かれたようです。
このシュタイナー教育の体験が
「人を育てる」ということについて考える
とても良い刺激になっていたようです。
教師が語りすぎない理由 〜学ぶ主役は子ども〜
授業は生徒・受講生が主役です。
先生が一生懸命語っているときは
先生が主役になっていて
学ぶ側は受け身です。
思考も感覚も不活発です。
でも、
夢中になってやっているときには
自由な思考が活発に働いています。
そんなときに
先生が話すと
「邪魔」になってしまう。
学ぶ側がどれだけ
体と心と頭を活発に働かせるか
・・・ということが
学ぶ側が「主役」だということです。
学ぶ側が主役になると
先生の説明なんかより
はるかに多くのことを
自分で掴み取ります。
成長度も学びの深さも
全然違います。
シュタイナーアプローチが大切にする「学びの土壌」
シュタイナーアプローチにおいて、子どもたちが自ら学ぶ力を育てるため大切なことは以下です。
- 体験を十分にさせる
- 感じ、考える時間を確保する
- 説明を控える
- 待つ
- 良い問いかけをする
具体的には
- 子どもの自由時間を大切にする
- 子どもがやっていることを邪魔しない(見守る)
- 「どうして?」に対して「どうしてだろうね?」と返す
- 「教えて」に対して「ーーを試してみたら?」などと返す
小さな工夫で、子どもが変わる
こうした小さな心がけが、子どもを「学びの主役」にする教育の第一歩です。
石川華代のシュタイナーアプローチは、ただ知識を教えるのではなく、「人を育てる」という本質に触れる学びの場となっています。
まずは、できることをひとつだけでも日常に取り入れてみてください。
子どもが自分の力で学びを掴み取る姿に、きっと驚かされるはずです。