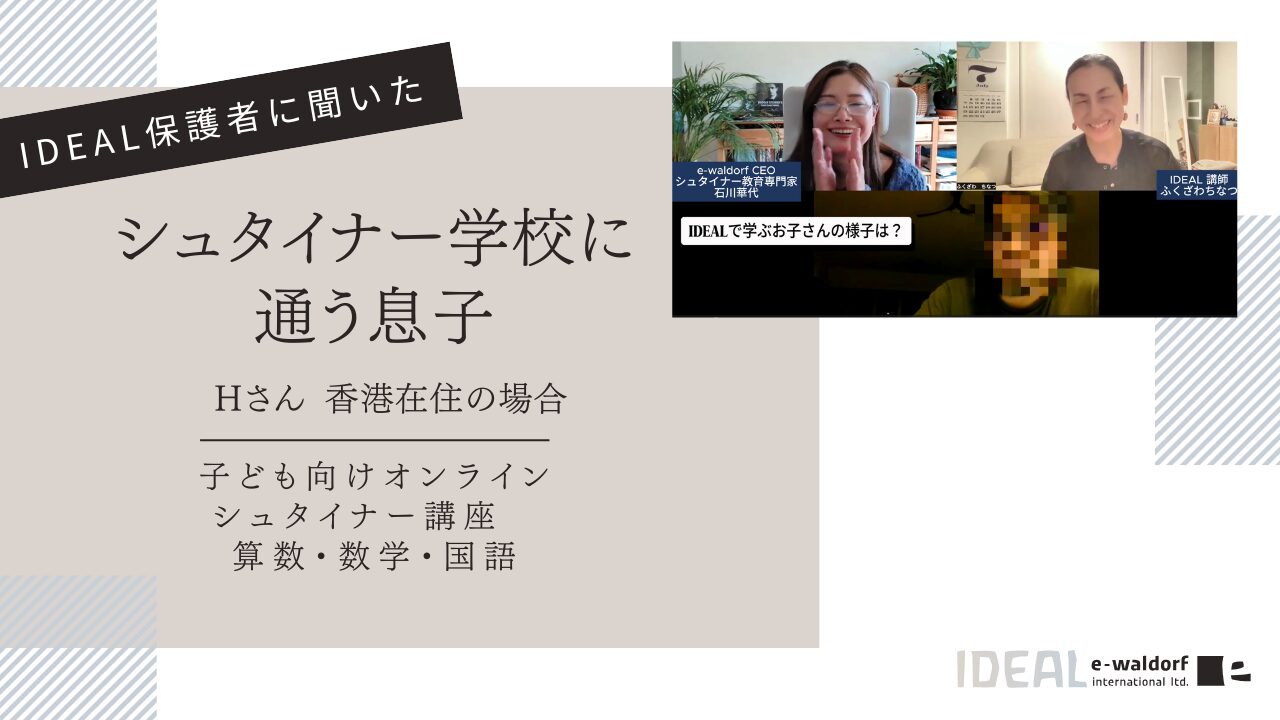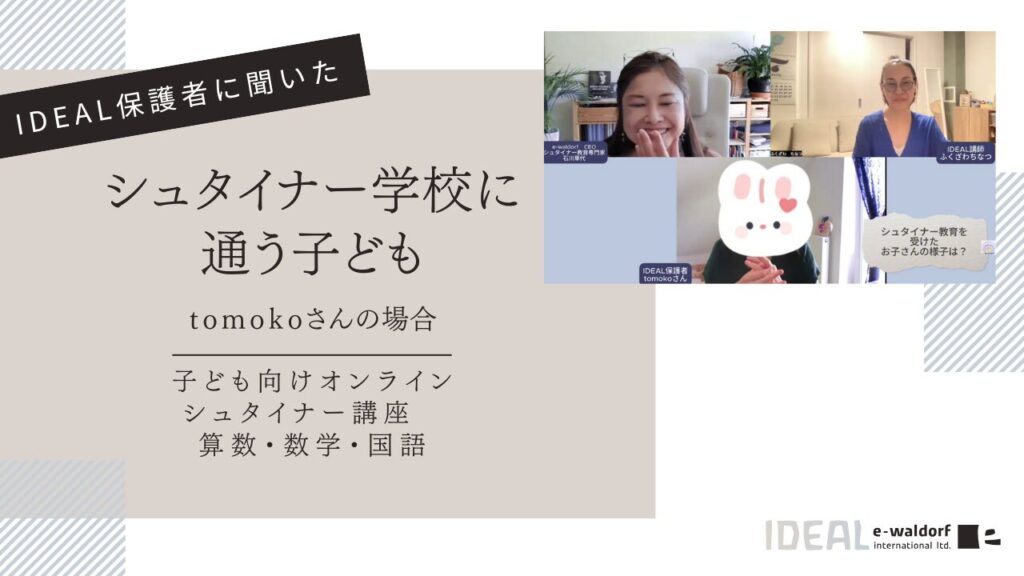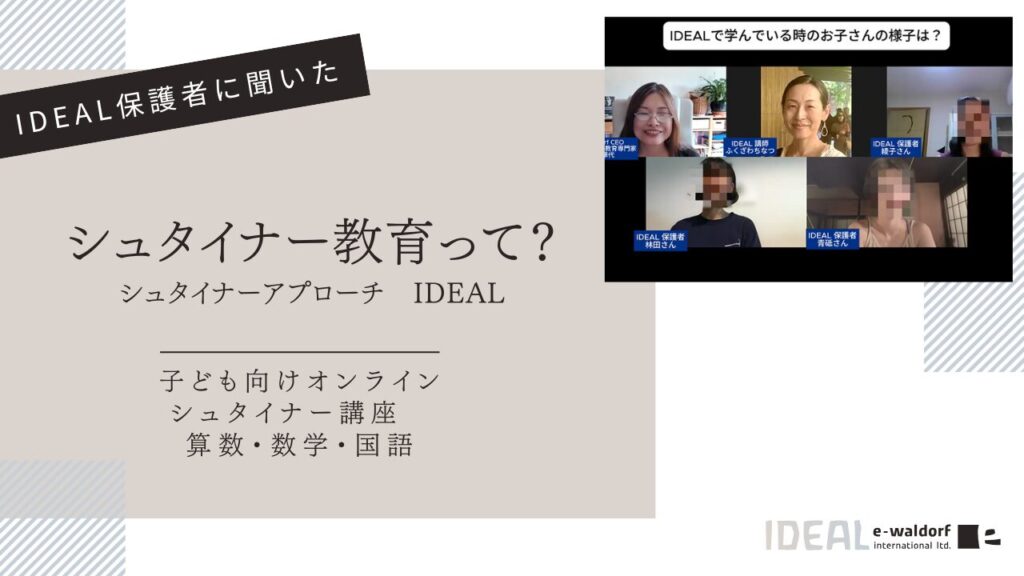「体験すると、世界の見え方が変わる。」
香港でシュタイナー学校に行きながら、オンラインシュタイナー教育のIDEALで学ぶSくん。
シュタイナー教育専門家・石川華代とIDEAL担当講師・ちなつ先生が保護者S.Hさんと対談しました。算数レッスンが日常に生む“問い”や、進路選びをしなやかに考える視点をお届けします。
対談はyoutubeでもご覧いただけます。
この記事は、IDEAL保護者ヒアリング(香港在住 S.Hさん)の内容をもとに再構成したものです。実際の対談をそのまま掲載したものではなく、読みやすさのために抜粋・要約・編集しています。
シュタイナー学校と家庭でのシュタイナーアプローチ
Sくんは現在、シュタイナー教育の学校に在籍しています。担任の先生が長く伴走してくれる環境に満足しつつ、さらに算数への知的好奇心を伸ばすため、シュタイナーオンライン家庭教師POTENTIAL(ポテンシャル)の個別レッスンを受講しています。
香港では英語環境が中心のため、日本語で学べる時間を持てることも、ご家庭にとって大きな価値になっています。
「学校ではまだ出会っていない“重さ”や“長さ”、“割合”といった内容を、レッスンの中で体験から学んでいます。例えば、(手作りの)はかりを使っておもりを量ってみたり、日常の中ではなかなか経験できない活動をしているんです。そうした学びの積み重ねがあるからか、街でパーセント表示を見かけると『あれってどういう意味なの?』と自分から質問してくるようになりました。単なる知識の理解にとどまらず、生活と数字や概念が結びつき、自分から考える姿勢が育っているのは大きな変化だと感じています」(S.Hさん)
子ども本人のシュタイナーオンライン家庭教師 POTENTIALの満足度
「本人に『何が好きで、何があんまり好きじゃない?』と聞いたら、『全部好き。先生がやってくれているのが楽しい』と即答していました。『嫌いなことはない、全部楽しい』と言っていたので、本当にレッスンを楽しんでいるのだと思います。
いろいろな新しい概念や考え方がスムーズに入ってきていることが、彼にとって心地いいのだろうと感じています。『こうしてほしい』という要望よりも、『今が楽しい』という気持ちが強いようで、それが2年目以降も続けたいという意欲につながっているのだと思います」(S.Hさん)
保護者が大切にする教育観
S.Hさんは、ご自身が日本の一般的な教育を経験した立場から、既存の教育システムの限界を強く感じています。特に、記憶偏重になりがちな点、そして知的好奇心が育ちにくい点を懸念しています。
「僕らが子どもの頃に受けた教育をそのまま押し付けても、子どもたちは20年後の社会を生きていくわけです。世代間の40年のギャップを考えると、今の既存の教育だけでは厳しい。せっかくなら興味のあることを、自分で深く掘っていけるような思考回路を育てたい」(S.Hさん)
そのために選んだのが、シュタイナー教育の学校と、POTENTIALでの算数学習です。体験を通して概念を理解し、学びを生活に結びつけることを大切に考えています。
具体的には、家庭でこんな場面があったそうです。
カップケーキが17個あったとき、Sくんとお姉さんで分けることになりました。最初は8個ずつ分け、最後の1個が余ったときに、自然と「半分にする」という答えが出てきたのです。この経験を通じて、小数の概念を頭で覚えるのではなく、実感として理解していました。「数字や概念が生活と直結することで、『自分で考えて解決できる』という感覚が育つ。これが将来どんな環境に進んでも役に立つはずだと考えています」(S.Hさん)
シュタイナー教育の広がりと認知、特徴
S.Hさんは、親戚がアメリカでシュタイナー教育を受けていることに触れながら、「シュタイナー教育の広がり方はどのように見えているのか?」と質問し、石川がシュタイナー教育の現状や特徴など回答します。
「世界にはすでに1000校以上、幼稚園を含めれば2000校ほどあります。数の上では少なくないのに、“普通の学校教育の延長”としてはあまり認知されていないのが現実です。『ちょっと違う教育』という壁や誤解が先に立ってしまうことが多いですね。」
「本当に優秀な子供たちこそ、本当に基本のところを育ててあげたら、どんどん伸びていく、その可能性を広げてあげられるから、私は本当にシュタイナー教育は実はすごいエリート教育だよなっていうところも思っています。
もちろんサポートが必要な子供たちにもすごい価値があるけれども、決して勉強のできない子が行く学校では全然ないですよね。」
「心の部分が育っている、人間性としての心の部分が育っているっていうことと、 本当にその子の本当に持っているものを生かしていく、 知識詰め込むだけではなくて、そして本当に自体の子を見ていて思うのは、 どんな問題が降りかかってきても、ダメだって思わないんですよね、 これできないって思わずに、 考えてやっていけば解決するよっていうスタンスがもうすでに身についていて、 実際にやっちゃうんですよね。 そういうのがすごい例外なく、みんながそういう状態になっていくので、 本当にそれもう人間としてものすごい強いことじゃないですか。」(石川)
暗記に偏る学びへの疑問
S.Hさんは、今の教育が「暗記教科になってしまっている」ことに強い違和感を持っています。
「公式とかを全部丸暗記しているだけの子が多いですよね。メディアでもコサインやサインなんか覚えても使わないなんて言われますが、実際には日常の中で自分は使っているので、そういう言い方は良くないと思うんです」(S.Hさん)
石川もこの点に深く共感します。
「数学をやっていても“考える力”が育っていない。本当に何のために数学をやっているのか?問題は解けても、覚えているだけでは考えていない。教育の意味そのものに疑問を感じてしまいます。公式そのものを覚えている必要はなくても、“考え方”を身につけているかどうかが大事です。日常生活の中で数学的思考は誰もが使っているんです」(石川)
さらにS.Hさんは、算数に限らず文章理解力の低下にも危機感を覚えていて、石川も同意しました。
youtubeにて「シュタイナー学校に通う息子」配信中
さらに詳しく聞きたい方はyoutubeをご覧ください。
シュタイナー学校へ行った場合の進路(石川の息子さんのケースなど)や、シュタイナー教育での音楽の位置づけ、シュタイナー学校に行くべきか?・・などの話が続きます。
youtubeにて「シュタイナー学校に通う息子」内容
- 00:00 IDEALで学ぶお子さんの様子は?
- 04:23 子どもの教育で大切にしていることは?
- 07:19 シュタイナー教育を選んだ理由は?
- 10:08 家での過ごし方は?
- 11:52 POTENTIAL(オンライン家庭教師)に求めること
- 18:51 シュタイナー教育の広がり
- 28:33 シュタイナー教育の魅力
- 31:25 海外のシュタイナー学校の進学
- 41:41 石川華代 シュタイナー教育との出会い
- 43:33 日本の数学教育や基礎学力
- 46:42 シュタイナー学校、行くべきか?
- 50:25 シュタイナー教育の音楽について
子どもたちの「わかった!」「楽しい!」という声は、学びの原動力です。この子ども向けシュタイナー教育 IDEAL(イデア―ル) 及びPOTENTIAL(ポテンシャル) の体験レッスンでは、 「子どもの好奇心を引き出し、成長を見守る」 特別な時間をお届けします。